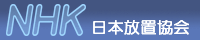礎(いしずえ)
夢のように思っていた21世紀を迎え、それでももう20年ちかくが過ぎていた。
生まれたころから不景気、不景気というため息を聞きなれていたから、大人になるまでそれが当たり前だと思っていた。
ただ、その不景気の中にも上下の波があって、自分はまだマシな波の上にいたのだとおもう。
政府から化学修士の称号を戴き、就職した技術系会社は一流企業の端くれくらいではあった。
入社して1年間は設計技術の習得を義務付けられた。
その会社の技術を手っ取り早く、包括的に感じるためにはそれが一番だから、という理由だった。
化学者の仕事とは思えなかったけれど、仕事ってたぶんそういうものだし。
コンピュータを扱うことには慣れていたから、とくに不満はなかった。
入社2年目、材料開発の部署に配属が決まった。
化学者としての自分にはまずまず、適正な配属といってよかった。
もしかしたらこういう、小さめの会社だからこそ、人事も新入社員の適性に心を砕いてくれているのかもしれない。
配属初日、人事の人に案内されて部署のフロアに行く。
この人が指導係だ、と示された人は、ひと回りくらい年上の男だった。
ていうか、爆睡していた。
始業のチャイムが鳴ると男は、おはようございます、と間の抜けた挨拶をして椅子に座りなおした。
眼鏡をずり上げ、ノートPC端末を開いて電源ボタンを押すと、ついでのように私の名前を確認した。
*
初日は社内案内と安全教育の予定だ。
自分と同じく新人を受け持つ後輩社員に、何をどうすればいいかと相談を受けていたが。
「適当にやるわい」と息巻いてろくに準備もしていなかった。
とりあえず「カッターナイフの使い方」など謎の資料をカラー印刷して携行できるようにしておく。
そして初日の朝、始業前に新人がフロアに集まる。
ポリシーとして「1分もサボらない代わりに1分も時間外労働しない」を掲げているから、
チャイムが鳴る瞬間まで狸寝入りを決め込んだ。
自分が新人を担当することになり、その新人は女の子だと、あろうことか数日前に、あろうことか風のうわさで聞いた。
挙句、前日まで何の音沙汰もなかったので、自分から部長に確認をとった。
さすがに顔と名前を忘れられたのでは心細かろうから、新入社員データを見て名前を何度もつぶやき、どうにか記憶する。
画像データは1 bitでなんだかよくわからなかったが。
技術部署に配属されたのだから、ゴツめの子だろうと推定した。
隣席にきれいな女の子が案内されてきたとき、狸寝入り/新人対応の切り替えに失敗し一瞬気絶。
いまだに貴族であり、そのまま仙人と化そうとしている自分に対する部長の策謀だと悟った。
わけのわからぬまま相手の名前を確認し、戦のごとくてめえの名乗りを上げた。
配属後の1秒1秒、何をすればいいのか不安であろうことはわかっていたが、細切れな質問と対応を指示することくらいしかできなかった。
とにかく計3名の新人を集め、社内ルールや部署ルール、一般注意事項などを話して聞かせる。
そして社内案内。
工場併設の会社だから、歩き方ひとつ間違うと大事故の元になる。
工場では帽子は絶対にかぶれ、禿げたくなければな、などとしどろもどろのギャグをかましながら広大な敷地を練り歩く。
*
先輩社員というものはもう少ししっかりしている感じだと思っていたが、男の言動はその予想を裏切った。
社の広い敷地を歩きながら、たしかにまともな説明や注意事項を話してはいる。
だけど1説明につき1個以上飛び出すおやじギャグがそのすべての緊張感を破壊していた。
新人を和ませるためだろうかとはじめは思ったが、すぐに分かった。
これはこの男の地だ。
この男、めんどくさい。
――数週間の時間が過ぎた。
OJT期間だからか、基本的に社内にいる時間は男と一緒に行動することが多い。
一人で出来るであろう作業の時でも、男は必ずと言っていいほど付きまとってくる。
私を心配してか、己の私情によるものかは分からないが。
とりあえず作業は男が率先してやってくれるから、楽ではあった。
何時間も設備の動作を見るだけ、という仕事もあったから、めんどくさいおやじギャグも慰みにはなった。
時折、おやじギャグに笑ってしまうと、男は目を輝かせて追撃してくる。
超めんどくさい。
でもまあ、暇つぶしにはなった。
悪くはない、と思えるようになっていた。
時には男のギャグに素直に笑い、また男を笑わせようと試みるようにもなっていた。
肩の力を抜いてみれば、なぜこんなに気が合うのかと、不思議に思うほどになっていた。
そんなことをしていると別の先輩社員から「なにイチャついてるんすか」とか言われたが、
学生の頃に想像していた無機質な会社員生活とは無縁といえた。
あるとき、珍しくまじめな顔になった男に言われた。
あなたは優秀な社員たり得る。
経験上、あなたのような人は、社内のいろいろな部署を渡り歩くことになる。
ゆえに、一緒に働ける時間はとても短いだろう。
今のうちに学べることを学び、聞きたいことはすべて聞いておきなさい。
と。
少しだけ寂しい思いがしたのは、我ながら不覚だったと思う。
確か男も遠方の工場の工程改善のため単身で派遣されたり、
新設の技術開発部署に植民されたりと諸行無常の社歴を持っていると聞いていた。
1年が過ぎ、2年目の半ばまでは、ほとんど腐れ縁のごとく男と一緒に仕事をした。
そしてある日、本当にとつぜん自分の社歴が大きな転換期を見るのを感じた。
部長に呼ばれ、北米に飛んでもらいたいと告げられた。
社命だったから否も応もなかった。
そもそも業務命令による異動には従わなければならないと、社則に明記されていた。
男は寂しそうな眼をしたが、やはり否も応もなく、必要な手続きを淡々と説明してくれた。
そして北米に飛び、数年後には北米の別の拠点に飛び。
日本に帰ってくる頃には肩書がつき、ついでにフィアンセもでき、絵にかいたような満帆の人生にあることを認識していた。
ひさしぶりに男をからかってやろうと思い、社内名簿を浚ったが、男の名はどこにもなかった。
*
意識が戻ると、寝台の上だった。
男は反射的に、手術室だと思う。
それほどその部屋は白く、明るく、清潔だった。
ただ、いつから意識がなかったのか見当がつかなかった。
――気配。
白衣の痩せメガネが顔を覗き込んでくる。
メガネどうし見つめあうのも気色が悪い気がして、自分のメガネを探ろうとする。
しかし、手は動かなかった。
感覚はしっかりしているが、寝台に拘束されているらしい。
相手の痩せメガネが言う。
「お疲れさまでした。あなたはあなたの任務を見事、完遂されました」
意味が分からないので、表情で「?」を作る。
「新人の女の子を指導していたでしょう。彼女を一企業戦士として育て上げ、幸せな人生を歩ませる。
その礎となることが、あなたの任務でした。
あなたはその任務を立派に遂げられた。
彼女は今や、あの会社の管理職であり、また……社会的にも信頼される身の上となった」
新人、女の子、彼女。
代名詞が、男の脳裏でゆっくりと実像となる。
「まだすこし混乱されているかもしれませんね。
すこし、雑談でもしましょうか」
痩せメガネは男から視線を外し、思い出すような口調で話し始めた。
「人間というのは不思議なものです。
生物学的にみれば皆ほとんど同一の脳を持ち、その脳があらゆる意思決定を司る。
そう考えると、すべての人間が同じ性格で、同じ嗜好を持つほうがむしろ、当然のようにも思えます。
しかしご存じの通り、人間の思考パターンは千差万別だ。
これはどこから来るものなんでしょうね」
痩せメガネが少々芝居がかった仕草で男から視線を逸らす。
「このあたりの研究は科学というより、むしろ心理学で扱われるものです。
――ご存じですか、人間のものの見方、感じ方といった分野では、科学より心理学のほうがはるかに先を行っているのです。
たとえばひとつのリンゴにしても。
リンゴを目の前にしたとき、なぜひとはそれがリンゴだとわかるのか?
科学では説明のつけようがありません。
これは認知心理学の得意とするところです。
それによれば、人間はまず、リンゴの輪郭――つまりおおざっぱな形を認識する。
そしてその輪郭のうち、曲率が急激に変化する部分や、角の部分。
これらを抽出・検知し、組み合わせることで、それがリンゴとしての特徴を満たしているかを判定しているんだそうですよ」
男が怪訝な顔をすると、痩せメガネは言葉を加える。
「つまり生まれてから、これがリンゴだよ、と見せられた物体の輪郭の、特徴的な部分を我々は学習している。
つぎに未知の物体を見せられた時、我々はその輪郭を見て、学習したリンゴの輪郭と比較する。
似ていればリンゴだと思う。
――だから、食品サンプルだろうと絵にかいたリンゴだろうと、リンゴの形をしていればリンゴだと思ってしまうんだ」
カップから液体を飲む間だけ、痩せメガネは黙っていた。
「さて、なんでこんな話をしたかというと、あながちただの雑談ではない。
新入社員の子、覚えているでしょう。
あの女の子を無事に、幸せな企業戦士として育てるのがあなたの任務だった。
そのために、あなたは派遣されたんです。
どうでしたか、あの子。
きれいで明るくて朗らかで、あなたから見ても魅力的だったんではないでしょうか」
痩せメガネがにやりと笑うが、すぐにもとの無表情に還る。
「こう考えてみてください。
あの子がご自分の娘だったとしたら、どうです。
わけの分からん会社に放り込まれる。
そこにはわけの分からん同僚や上司、男どもがうじゃうじゃいる。
どう思います、父親として」
男はわずかに顔をしかめる。
「そうでしょう。
それが普通の感覚です――父親としての。
だから実際、彼女の父親も、同じ心配をしました。
しかしそうはいっても、まさか娘につきっきりでいるわけにはいかない。
至善の策が成らねば、次善の策。
自分が娘のそばにいてやれないのであれば、信頼できる代役を立てればいい。
理想的な先輩社員を送り込み、付きっ切りで指導させればよろしい。
発想は突飛かもしれんが、まあ、そりゃそうだと思っていただけるでしょうか」
仕方なくうなずく。
「そこで次の問題が生ずる。
理想的な先輩社員、とはどんな人間なのか、ということだ。
残念ながらこんな哲学的な問題に一意の答などない。
しかし、近似解はある」
ふたたび痩せメガネが液体を飲み下すのを、黙って待つ。
「要は、気が合う奴を送り込めばいいわけだ。
気が合うとは、つまり対象の人間に対して共感力の高い人間、と言える。
共感力とは何で決まるのか?
そのあたりは発達心理学に踏み込むことになるが、話は簡単だ。
人間はリンゴの形を学習するのと同じように、他人の心の構造もまた学習する。
つまり長い間いっしょにすごした人間に対しては、おのずと共感力が高くなると考えられる。
さらにその人間が遺伝的に近い間柄ならば、ニューロンの発火性質も類似点が多くなる。
つまり――」
痩せメガネが男を直視する。
「彼女の親であれば、自然、彼女と共感する確率が非常に高い。
彼女と長い間同じ時間を過ごし、遺伝的にも近しいわけだから。
――もちろん、実際の親は彼女と歳が離れすぎているから、様々な反発もある。
だが、彼女の親と全く同じ思考パターンを持つ人間が、それほど歳の違わない先輩として現れたらどうだろうか」
痩せメガネに見据えられ、男は動けなかった。
「彼女の父親はアンドロイドを一体、発注して、彼女の会社に先輩社員として送り込んだ。
そのアンドロイドには父親の思考パターンを模倣した脳神経プログラムが組み込まれていた。
そのアンドロイドは思惑通り、彼女とよく気が合い、彼女をスムースに成長させた。
そのアンドロイドが、君だ」
男は動けなかった。
痩せメガネが非情の宣告ののち、その場を離れ、なにか機械の操作を始めても、何も言えなかった。
指一本、動かす気になれなかった。
「もう一度言う、君はよくやってくれた。
そして、これで終わりではない。
君には次の職場に行ってもらわなければならない。
もちろん、新しい人格として。
いまから君をフォーマットし、新しい人格をインストールする。
大丈夫、痛くもかゆくもない、少し眠くなるだけのことだ。
――じゃあ、な」
男の視界が真っ白になり、体が硬直するのを感じた。
次いで暗闇が訪れようとするとき
「――」
男は彼女の名前をもう一度だけ、呼ぼうとした。
了
たまにはこんな、徒然狸 ―タヌキの日記―
筆者は盲導犬を尊敬し、個人的に応援しています。
中部盲導犬協会:http://www.chubu-moudouken.jp/
日本盲導犬協会:http://www.moudouken.net/